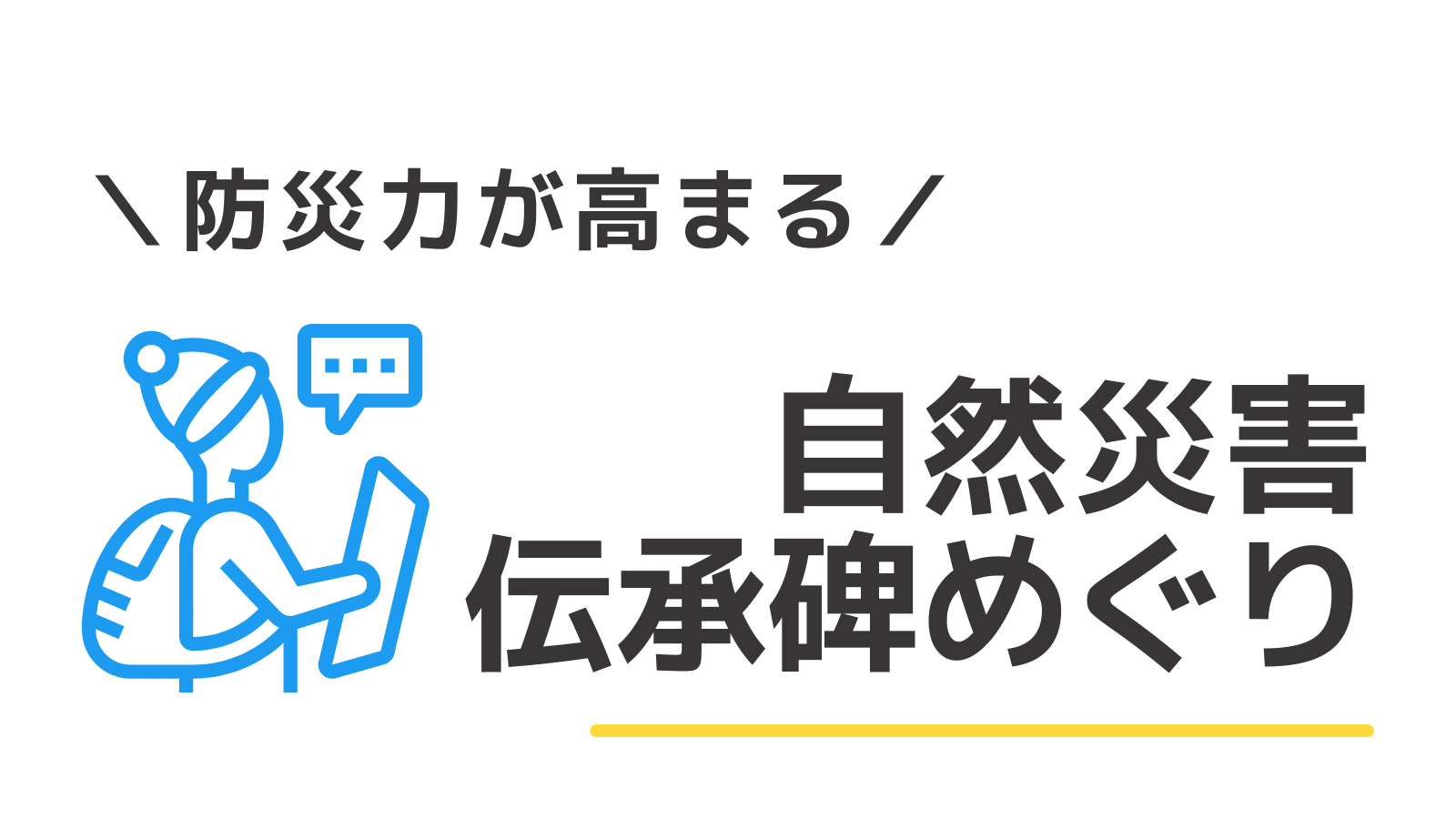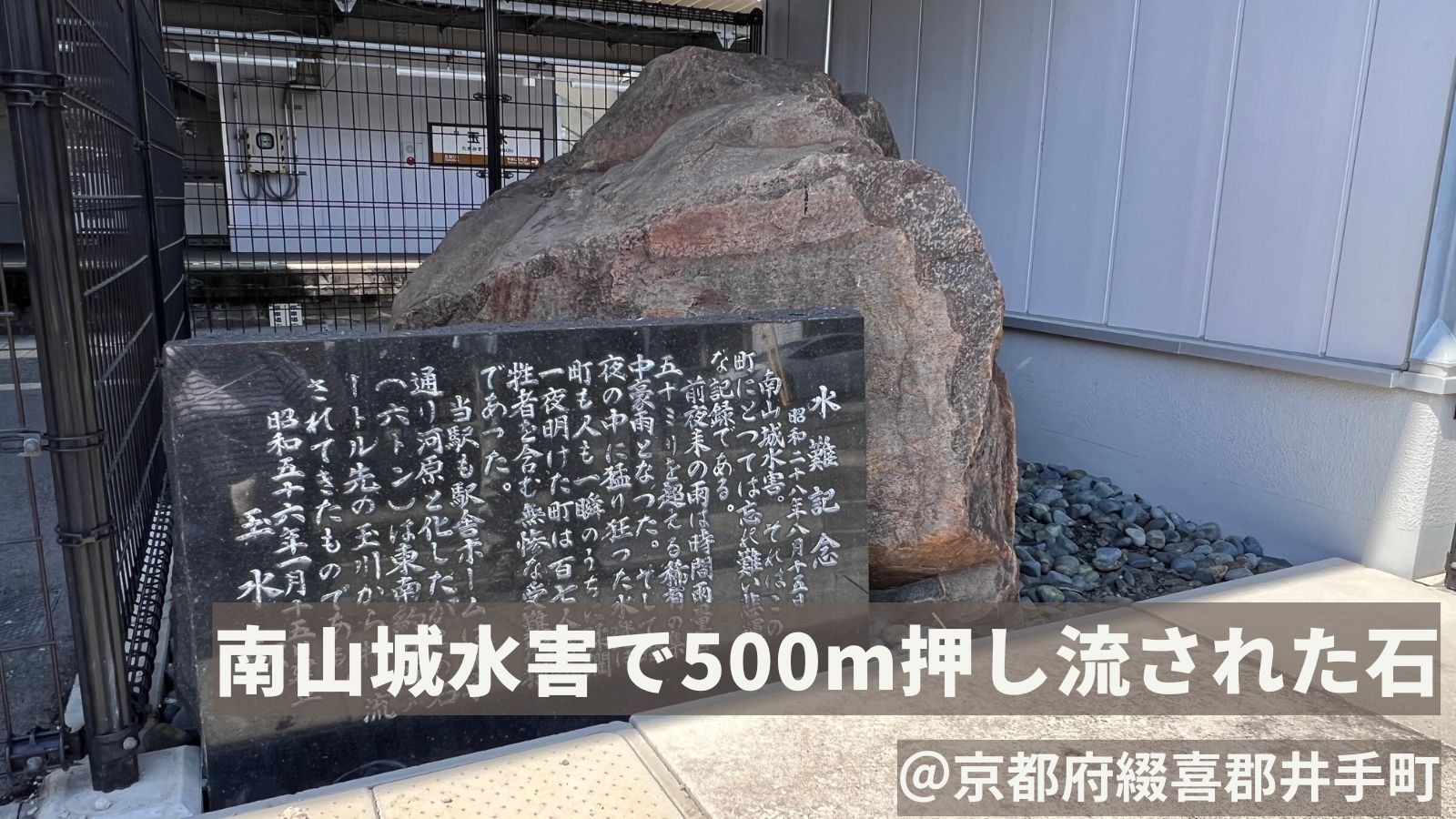和歌山県|紀伊半島は台風も多いんです

こんにちは。結(Yui)です。友人のベルちゃんと一緒に自然災害伝承碑をマップにピン建てしていくプロジェクトを一緒に行っています。
紀伊半島大水害
2023年5月6日 (晴れ時々曇り)
さてさて、前回に引き続き今回も和歌山県の碑ですよ~。今回は、比較的新しい碑で2014年に建てられた「紀伊半島大水害」です。前回の碑は、地震と洪水災害の碑でしたが、今回は台風です。紀伊半島は台風も多いですよね。過去にもジェーン台風(1950年)、伊勢湾台風(1959年)、第二室戸台風(1961年)など様々な台風が和歌山県を襲っています。そして、その台風の中でも比較的新しい2011年の台風第12号による豪雨では、熊野川や相野谷川などが氾濫したり、土砂崩れが起こったりしました。それに伴い、1,004棟もの家屋が被害を受け、1名の方が死亡しています。この台風第12号による豪雨での災害を伝承しているのが、この「紀伊半島大水害」の碑です。
ところでこの「紀伊半島大水害」の碑は、浸水最高水位を示しているのですが、残念ながらこの自然災害伝承碑には浸水最高水位の記載がありませんでした。なので結(Yui)が自分で国土地理院さんの地図で標高を調べてみたのですが、この辺りは大体11~12mぐらいかと思われます。国土地理院さんの地図は標高も調べられるんですよ(標高は東京湾平均海面からの高さです)。

実際行ってみるとわかるのですが、この牛鼻神社は海側より少し内陸にありまして、西側に流れている熊野川と、北側を通っている相野谷川がちょうど合流するところに位置しています。つまり川に挟まれています。もし川の水位が大雨などによって上がり、両方の川が溢れれば…恐ろしいですね。紀北町では、災害を風化させることなく、伝承していくために最高水位を示す7基の自然災害伝承碑を立てたそうです。町の目につきやすいところに、こういう伝承があるのは地域の皆さんへの防災意識の高まりにも、観光客の防災意識の高まりにもつながると思いますので良いですね。

最後ですが、この自然災害伝承碑がある神社の名前が、牛鼻神社というかなりユニークな名前だったので、名前の由来を調べてみました。紀宝町の広報誌を見ると”牛鼻神社は、神武天皇東征の際に牛の鼻を繋いだとも伝えられており、紀州地方最古と言われるほど歴史のある神社です”とあります。牛の鼻を繋いだから牛鼻神社なのでしょうか?どちらにしろ由緒ある神社のようですね。牛の守り神として地域の農業に携わる方々から信仰があったようで、牛の銅像もありましたよ。自然災害伝承碑を見に行かれる際には、牛さん銅像も見てみてください。
紀宝町HP>>広報紀宝町2月号(平成31年): https://www.town.kiho.lg.jp/wp-content/uploads/2019/01/d2c11b43c48abf347784e7f08ed36062.pdf
おまけ – 道の駅紀宝町ウミガメ公園
和歌山県と言えば海。そしてここには、ウミガメと出会える道の駅があります。それがこちら「紀宝町ウミガメ公園」。こちらはウミガメが水槽で泳いでいる様子を見ることができます。いつもなのかどうかは分かりませんが、結(Yui)が行ったときは、何匹かのウミガメちゃん達が外に出ていました(もちろん平らな水槽に入ってましたが)。なのでこんなに近くでウミガメを見ることができたんですよ~。

ハワイではウミガメは幸福を呼ぶ海の守り神とされています。私はマリンスポーツをしないので、ウミガメさんに会う機会は少ないのですが(マリンスポーツしてても会う機会は少ないのかもしれませんが)、今回はすごく近くでウミガメさんが見れて、とても良かったです。
結(Yui)でした。ではまた~☆
道の駅紀宝町ウミガメ公園: https://umigame.info/